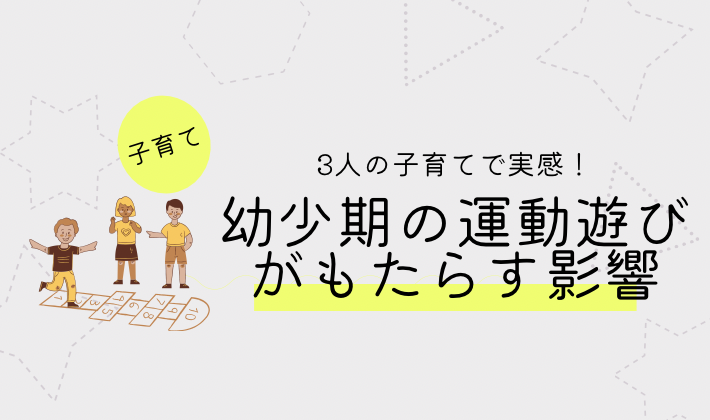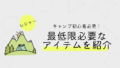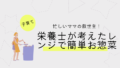子どもは身体を動かすことが大好きではありますが、
成長とともに
- 運動が好きな子
- 運動が苦手な子
と差が出てくるものです
実際、私も3人子育てをしてみて感じていることは、
幼少期の運動遊びで子どもの成長に大きく影響を与えると言うことです
出来れば
『運動が好きな子・得意な子に育ってほしい』
と言う思いから、運動を沢山経験させる方も多くいると思います
運動は運動が好きや得意だけではなく、
それ以外の子どもの成長にメリットになることが沢山あります
今回の記事では
・幼少期に運動遊びが大切さに気づいたきっかけ
・幼少期になぜ運動遊びが大切なのか
・自宅で簡単にできる運動遊び
について紹介します
今回の記事を読んでいただけると、
詳しく解説していきたいと思います
幼少期に運動遊びが大切さに気づいたきっかけ
気づいたきっかけ
私には10歳・7歳の息子、4歳の娘がいます
私が子どもとの関わり方の大切さに気づいたきっかけは、長男が年長の時でした
長男は3歳から保育園に入園しましたが
集団生活になかなか溶け込むことができずにいました

一緒に何か取り組むこともじっと座っていることも苦手
警戒心が人一倍強くいつも見学していることがほとんどでした
成長とともに変化してくるかもと様子を見ていましたが、年長になっても不安な要素は消えず
小学校入学前に一度発達検査を受けることを決意
検査の結果は、
正常範囲内ではあるけれども、得意不得意の項目の差が大きいことが原因でした
- 聞いて内容を理解するのが苦手
- 細かな作業が苦手
- 身体の筋力が十分発達していないと長時間座ることが苦手
このような点でした
不得意は経験が少ないだけであって、その子にあった関わり方次第で、不得意を伸ばすことは出来ると言うことでした
そのとき息子との関わりの中で大切なことは、理解できるようにゆっくり説明をすることや、沢山身体を使い運動機能を伸ばすことや指先の細かな運動を取り入れることでした
自分で出来た体験や成功体験が少ないから、自信がなく初めてのことに対しても警戒心が強くなりなかなかみんなと一緒に参加できない部分でした
この検査結果に、今までの自分と息子の関わり方に対して大きく反省をしました
それまでは夫婦ともに家族のためにと仕事中心のせいかつでした
子育ても祖母達に頼ってばかりでなかなか関わってあげられなかったことや祖母達も足が悪かったこともあり室内の遊びが多く、運動遊びなど積極的に取り入れてあげることが出来ずにいたことでした
子どもは勝手に成長していくと、どこか楽観的に考えていた部分がありました
日々の関わりの積み重ねが、
子どもの成長に大きな影響を与えていることに気づかされたことが大きなきっかけになった出来事でした
出来事をきっかけに変えたこと
子どもにとってどう関わることが成長にいい影響を与えるのか、自分なりに学びながら少しずつ取り入れていきました
下の二人の子育ては、長男の時と比べると大きく変わりました
【出来事をきっかけに変えたこと】
・身体全身を使った外遊びを増やしたこと(公園や自転車で散歩など)
・指先を使った運動遊びを取り入れたこと(折り紙を折ったり、切って貼ったり、パズルなど)
・下2人からは未満児からこども園へ

・運動の好き嫌い
・学習や遊びに対しての集中力の違い
・折り紙など細かな作業の得意不得意
・想像力の違い
・精神的な成長の違い
幼少期になぜ運動遊びが大切なのか

なぜ幼児期に運動遊びが大切なのか
運動遊びを通して、幼少期は特に以下の点に大切な時期だからです
1.身体作り
2.心づくり
3.仲間づくり
これらを学ぶのは、遊びという刺激を通して学ぶからです
人は学ぶためには、繰り返し繰り返し体験することで学習していきます
身体づくり
赤ちゃんの時は生まれてすぐは、寝てばかりで自分では何できない状態でした
その状態から徐々に寝返りの練習から始まり、ハイハイし、つかまり立ちをし、歩けるようになるまでにも繰り返し繰り返し同じ動作を繰り返し習得していきます
走ること、ボールを投げること、ゆっくり歩くこと、思いっきり走ること、走る速度を調整することだって
全てはどれだけ動作を繰り返し体験し、習得してきたかで大きく差が出てきます
何も出来ない状態から出来るようになるには、経験次第と言うことなのです
長時間座るのだってお腹や背中に筋肉がなければ、長時間同じ姿勢で座ることだって困難なのはあたりまえのことだと言うことです
繰り返し繰り返し同じ動作をすることでその動作に必要な筋肉も育っていくからです
幼少期は特に遊ぶことが仕事です
遊びを通して、身体の使い方を学び、必要な筋肉を育て、遊びの中で自分で工夫する楽しさを知り、想像力を深めていきます
そのためには、子どもが熱中できる環境や想像力を深められる遊びを大人が提供することや出来る環境を整えることが大切です
心づくり
心の成長も同じです
何かに挑戦するとき、成功体験が多くある子のほうが、自分で乗り越えようとする原動力も大きくなり、自発的に新しいことにチャレンジできる子になります
これは自己肯定感を育むためには、必要な課程になります
そのため、遊びの中で『できた』を沢山経験させてあげることで、大人になったとき自分の人生を自分で切り開いていける自立した心へと成長していきます
仲間づくり
仲間作りも子どもは遊びを通して、仲間との関わりの中で学んでいくことも多くあります
遊びの中で、仲間と遊ぶことの楽しさを知り、仲間とどう関われば上手くいくのかも体験を通して学んでいきます
それだけでなく、どんな環境で人と関わってきたかによって、いつでも自分の意見を聞いてくれ受け入れてくれる体験を多くしてきた子は、安心して自分の意見をひとに伝えることが出来るようにとなります
これは親との関わり方でも大きな影響を与える部分でもあります
講義に参加し感じたこと
この講義を聞き、改めて長男が苦手だったことは、環境が大きく影響していたことを実感させられました
・全身を使った運動遊びをしてこなかったから、いざやっても上手く出来ないから運動に苦手意識に繋がってしまった
・長時間座ってられないのも筋肉が上手く発達していないことが原因
・細かな作業が苦手なのも(折り紙が折れない)指先を動かす遊びをあまりしてこなかったこと
・『できた』と達成感が感じられる経験をもっと沢山経験させてあげることで精神的な成長に繋がる
・幼少期の遊ぶことであられるメリットが沢山あること
いくつになっても遅くはありませんが、もっと早くから意識的に取り組めていたら長男にとっての苦手を軽減してあげることが出来たのでは感じています
今からでも苦手の原因が分かったことで、何をサポートしてあげることがいいのか具体的な方法が分かるようになりました
自宅で簡単にできる運動遊び
自宅にあるものを代用して出来る遊びを紹介します
新聞紙あそび
新聞紙遊びでは、いろいろな部位を使った遊びか可能です
・新聞紙を手で破いたり、ちぎったりして、指先を使い感覚を楽しむ遊び
・新聞紙を広げ投げ、ひらひら落ちてくる新聞紙をキャッチする遊び
・紙飛行機を作って飛ばす
・新聞紙をぐちゃぐちゃに丸め、新聞紙ボールを作りボールで遊ぶ(壁に的を作り狙って投げるなど工夫するとより楽しさUP)
新聞紙があれば、指先を動かす運動~全身運動まで幅広く遊べます
タオル遊び
タオルもどの家庭にもあるはずです
・タオルを落とさないように頭に乗せてバランス感覚を楽しむ遊び
・親と子どもでそれそれタオルの端を持ち綱引き
・タオルを手で振り回し手首の運動や肩の運動遊び
・タオルを縛ってキャッチボール遊び
タオル遊びも工夫次第で、幅広い遊びが楽しめます
外部リンクですが、参考になる記事を見つけたので貼っておきます↓
まとめ
私の子育ての経験を通して、特に幼少期の子どもの運動遊びが、子どもの成長に与える影響の大きさを実感しました
もっとちゃんとやっていればと後悔しても、過去は戻ってきません
大人の関わり方次第で、子どもの成長は大きく変わることを実感しています
そのときの成長段階にあった遊びを取り入れ、子どもが才能を最大限引き出せる環境を整えてあげることの大切さを再認識しました
是非子育て中のママに幼少期の運動遊びの大切さを知っていただき、子どもにとって成長をサポートできるように子育てに活かして見てください
子育て関連オススメ記事↓